農地転用の際に必要な手続きは?【宮城県の場合の留意点も解説】
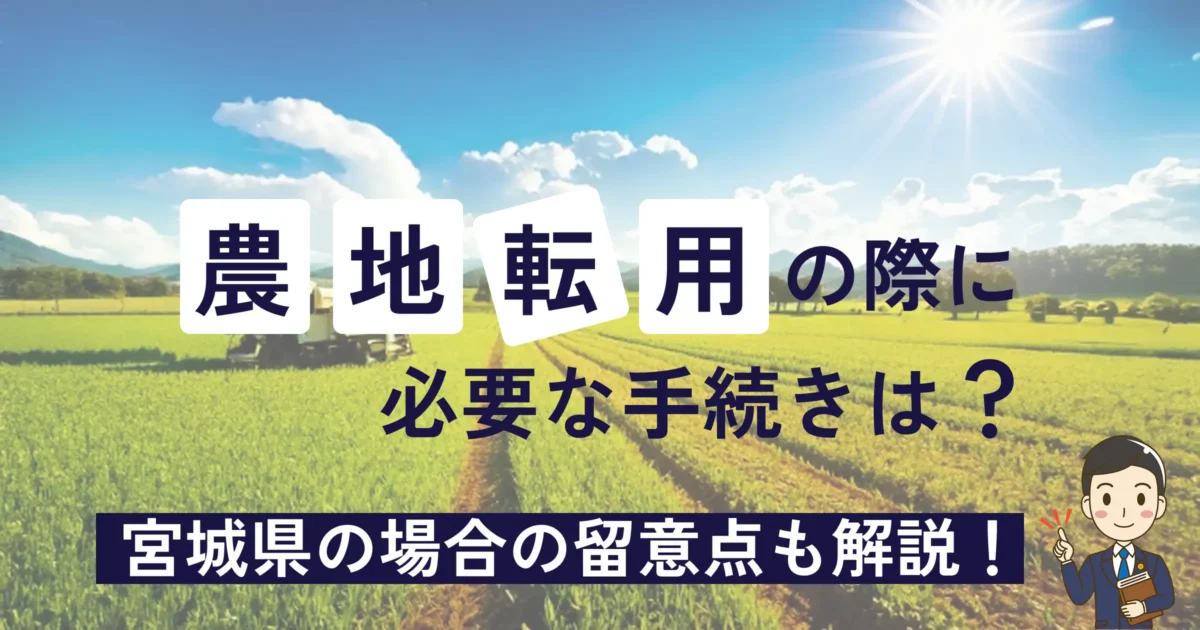
目次
農地転用とは
農地転用とは農地を住宅地・駐車場・導水路・学校・工場・倉庫・病院・太陽光発電所・廃棄物処理施設など、農地以外に転換することです。
日本は建築自由の原則がありますが、農業新興の観点から例外的に農地の転用は農地法により制限されており、自由に農地を農地以外に転換することはできません。
農地には、農用地区域内農地(農業のために利用していくべき土地として指定された農地)や市街化調整区域の農地(市街化をしないよう抑制された区域の農地)といった種類があり、土地の種別によって農地転用許可のハードルが変わってきます。
以下で、農地転用許可制度について具体的に解説していきます。
農地転用の申請者
自分自身の農地を転用する場合
農地法4条に基づき、農地の所有者が自ら申請を行います。
自分の所有する畑に自宅を建てる場合等がこちらに該当します。
別な所有者の農地を権利移転・賃借する場合
農地法5条に基づき、農地の所有者と転用事業者が共同して申請を行います。
例えば以下のようなケースが該当します。
・農地所有者Aさん:仙台市郊外に水田を所有。高齢のため農業を続けるのが困難になった。
・転用事業者B社:住宅地開発を計画しており、Aさんの土地を購入または賃借し住宅団地を造成したい。
上記の例の場合、農地所有者Aさんと転用事業者B社が共同で署名をして申請します。
【参考】
農地法第4条(農地の転用の制限)
農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地転用の申請先(許可権者)
農地転用の申請先(許可権者)は、都市計画法に基づく土地の区域および転用する農地の面積により定められています。
市街化区域の場合
市街化区域とは
市街化区域とは、都市計画法に基づき、既に市街地を形成している地域や、将来的に優先的に市街化を進める地域として指定された区域です。
市街化を進めることが前提の地域のため、原則として許可は不要で、農業委員会への届出で転用することができます。
申請先
市町村の農業委員会
※開発面積が1000㎡を超える場合は、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要になります。
市街化調整区域の場合
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて市街化を抑制された地域です。
原則宅地や商業施設の建設が禁止されているため、農地を転用する際には厳しい基準をクリアする必要があります。
申請先
市町村農業委員会を経由して都道府県知事に申請
※農地転用面積が4haを超える場合は、都道府県知事を経由して、農林水産大臣の許可が必要になります。
農業振興地域内農地の場合
農業振興地域内農地とは
農業振興地域内農地とは、農業振興地域整備計画で農業用として利用すべきと指定された農地です。
農業振興地域整備計画は農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき市町村が定めたもので、概ね10年先を見通して作成されています。
農業の振興を図るために必要な事項を定めた公的な計画であるため、その趣旨から基本的に農業振興地域内農地の農地以外への転用は禁止されています。
申請先
市町村農業委員会を経由して都道府県知事に申請
【参考】
都市計画法第29条(開発行為の許可)
農業振興地域制度の概要
農地転用制度の2つの基準
立地基準とは
下記の図で上から順に許可の難易度が高いです。
転用しようとする農地がどのような区分になるかはお住まいの市町村の農業委員会で確認することができます。
また、原則不許可の区域の場合、例外に該当するか、区域変更の可能性があるか等を確認し、ご自身の土地の農地転用許可の見通しが立つかを事前に確認する必要があります。
| 区分 | 概況 | 許可の方針 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 市町村が定める「農業振興地域整備計画」に基づき、農業振興地域内に指定された農地。 | 原則不許可 (農振法第13条2項の条件を満たす場合可能) |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内にある、特に良好な営農条件を備えた農地 | 原則不許可 (公共事業等公益性が認められれば許可) |
| 第1種農地 | 良好な営農条件を備えている農地。 | 原則不許可 (例外あり) |
| 第2種農地 | 市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない農地。 | 原則不許可 (第3種農地に立地困難な場合には許可) |
| 第3種農地 | 市街地化が進んでおり、農業以外の利用が進む可能性が高い土地。 | 原則許可 |
一般基準とは
立地基準を満たす場合でも、一般基準を満たさない場合不許可となります。
一般基準は、転用が確実に実行されるのか、周辺の農地に影響を及ぼさないかといったもので、主に以下の3つの観点の基準になります。
立地条件は土地の区域に基づくもので基本変更が難しい、裏を返すと事前に許可の見通しが立てやすいものです。
それに対して、一般基準は計画の実行性や周辺への影響への対処等が基準になり、やや対策が難しいものでもございますので、農地転用の専門家である行政書士に調査、申請手続きを依頼するのがおすすめです。
転用事業の計画が確実に実行されるか
申請者が転用後の計画を確実に遂行する能力と意志を持ち、具体的な実現可能性があることを求める要件です。この基準は、計画が中途半端な状態で放置されることや、転用目的が達成されないリスクを防ぐために設けられています。
より具体的な要件は以下のようなものです。
- 計画の詳細性
転用後の土地利用計画が明確で、用途や事業の実施内容が具体的に説明されている必要があります。例えば、住宅の建設であれば設計図や建設スケジュール、必要な資金計画などを提示します。 - 資金計画と財務能力
転用計画に必要な資金が確保されており、申請者または事業者が経済的に安定していることが示される必要があります。これは計画の実行可能性を裏付ける重要な要素です。 - 関係法令の遵守
建築基準法や都市計画法など、転用に関連する他の法令に適合していることが求められます。適切な許認可が取得済み、または取得予定であることを確認します。 - 事業遂行能力
転用事業を実施するための技術力や経験があることが評価されます。これには、過去の実績や事業計画を実行する体制の整備が含まれます。 - 期限の遵守
転用事業が遅延なく進行し、許可を受けた期間内に完了することが期待されます。これは農地転用が長期間未使用のままになることを防ぐためです。
周辺農地への影響
転用計画が隣接する農地や周辺地域での農作業に支障をきたさないかどうかを確認します。
例えば、転用後に排水や灌漑に問題が生じることで、近隣の農地が利用困難になるリスクを避ける必要があります。
一時転用の場合、確実に農地として復元できるか
イベント開催地、周辺施設の建設工事で仮置き場として一時的に使用する場合等を農地の一時転用と呼び、一時転用の後は、現状回復する義務があります。
一時転用後に現状回復が確実に行われることの証明として、農地復元計画書、農地復元工事の見積書等の書類が必要になります。
農地転用の手続きの必要書類
農地転用の手続きの必要な書類はお住まいの市町村や農地の種類によって異なりますので、確認して準備する必要があります。
(農地法施行規則第30条で必要書類が7つ列挙されているものの、実際には、7つ目に規定されている「その他参考となるべき書類」として、お住まいの市町村ごとにその他必要な書類が規定されています。)
以下代表的な書類になります。
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 農地転用許可申請書 | 農地の所在地、地番、地目、面積、所有者情報、転用目的などを記載。 |
| 位置図 | 転用予定地の場所を示した地図。 |
| 土地登記簿謄本 | 転用予定地の所有権や地目を確認するための書類。 |
| 土地利用計画図 | 転用後の土地利用目的や施設配置を示す図面。 |
| 公図 | 転用予定地の形状や地番、隣接地の状況を確認するための図面。 |
| 地積測量図 | 転用予定地の面積や境界を正確に示すための図面。 |
| 壯陽藥 data-align=”center”>事業計画書 | 転用の目的や計画、スケジュールなどを記載した書類。 |
| 転用予定地の写真 | 転用予定地の現況を示す写真。 |
農地転用の申請手続きの注意点
固定資産税が高くなる
農地として利用されている土地は、固定資産税の課税評価額が低めに設定されています。
農地を宅地や商業地などの用途に転用すると、その土地の課税評価額が用途変更後の地価に基づいて再評価されるため、固定資産税も高くなります。
また、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日なので、その点も考慮する必要があります。
賦課期日ぎりぎりに転用した場合(前年の12月30日等)、まだ収益を生んでいない場合でも、1月1日の現況で判断されますので、その年の固定資産税額が転用後の高い金額で計算されます。
申請後の審査に時間が掛かる
農地転用の審査にはある程度長い時間が掛かるため、余裕を持ったスケジュールで申請を行う必要があります。
届出のみのケースであれば随時受け付けで10日程度で返答がありますが、それ以外の許可が必要なケースでは1か月以上の日数が掛かります。
申請期日は各市町村毎月10日に指定されていることが多く、それを過ぎるとまた翌月の締め日の審査に回っていくので、申請期日も意識する必要があります。
また、農振除外の場合はさらに申請の締め日が少なく年に数回しかありません。
審査にも半年以上掛かるケースも少なくないため、さらに余裕を持った計画で準備する必要があります。
書類の不備等があるとさらに許可まで時間が掛かってしまうため、専門家である行政書士に依頼し、余裕を持って確実に申請の準備を行うことがおすすめです。
宮城県で農地転用する際の留意点
農用地区域の割合が大きい
宮城県は、優良農地保全の観点から、農用地区域の割合が大きく、県土面積の約2割を占めています。(令和 3 年 12 月 31 日時点)
農用地区域・・・今後 10 年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として定められた区域
農用地区域内にある農地は農振除外の手続きを踏まなければ基本農地転用できないため、宮城県における農地転用のハードルは高めだと言えます。
そのため、農地転用の際には、農地に応じて適切な計画、準備をして申請することが大切になります。
令和5年度土地利用の現況と施策の概要(宮城県国土利用計画管理運営資料)
まとめ
農地転用の手続きは関係機関とのやり取りや、農地に応じた調整、市町村ごとの申請書類の準備が必要になり、申請手続きが複雑なケースもあります。
我妻行政書士事務所では、農地転用に関する豊富な実績を基に申請手続きを代行いたします。
農地転用を考えている方は、お電話にてお気軽にご相談ください。
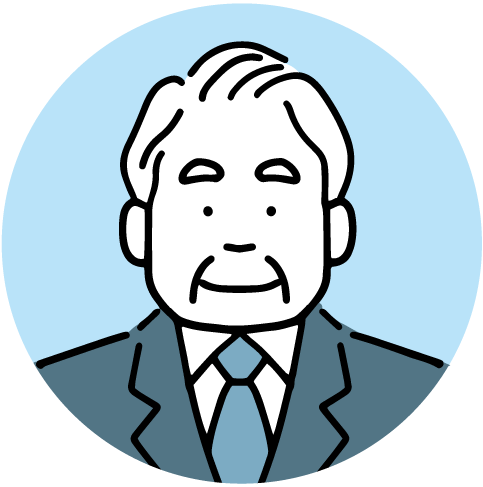
我妻行政書士事務所代表。宮城県行政書士会所属。
農地転用や古物商許可申請を中心にお客様の行政手続きをサポート。
 我妻行政書士事務所
我妻行政書士事務所